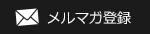生鮮食品や冷凍食品、ビーフジャーキーのような加工食品は、お土産には不向きなこともあって、現地でどんなパッケージに入っているか意外と知られていないのではないでしょうか。
こういった生活密着型の商品は、すぐに消費されることもあって、包装はあっという間に捨てられてしまいます。メーカーとしてもこういう消費サイクルの短いものにはコストをかけられず、機能重視になり、デザインとしてもおしゃれなものはほとんどありません。そのため、素敵なパッケージとして紹介されることもあまりありません。
でも実際に生活してみると、日本とはちょっと違う形や素材、包装形態が見えてきます。日常にしっかり溶け込んでいるからこそ、パッケージや売り方が生活の習慣にまで影響していることに気付かされます。
量り売りが地球とお財布を守る「Whole Foods Market」のナッツ売り場
アメリカのオーガニック系商品を多く取り扱う大手スーパーマーケットチェーン、「Whole Foods Market」に行くと、つい足を止めてしまう場所があります。それがこの、ずらりと並ぶ量り売りのナッツ売り場です。
アーモンド、カシューナッツ、ピスタチオ、ピーカン…色も形もさまざまなナッツやシード類が専用容器にぎっしり入っていて、見ているだけでワクワクします。
面白いのは、売り場に掲げられているサイン(画像1)。ナッツの種類や価格よりも大きく、"Save money(お金をセーブ)"、"Less packaging(省パッケージ)" と書かれているのです。「安く買えて、ゴミも減らせる」。まさにこの売り場の目的とメリットをストレートに伝えていて、それが「売り」になっているのです。

(画像1)
しかも、このコーナーにはナッツグラインダーも置かれていて、好みのナッツを選んでフレッシュなナッツバターを作ることも可能です(画像2)。自分に必要な分だけ作れるので、使い切れずに余らせる心配もありません。

(画像2)
アメリカの商品はとにかく一単位の量が多めです。もちろんそれがちょうどいい人も多いでしょうが、食べきれずに余らせてしまう人も多いはずです。量り売りはフードロスの解決にもつながりますし、無駄なパッケージも減らせます。実は「Whole Foods Market」に限らず、地元の小さなスーパーでも、規模は小さいながらこうした量り売りスタイルを採用しているところがあるので、これからも増えるかもしれませんね。
量り売りには衛生管理や鮮度維持などの課題がありますが、目の前に実物が山のように積まれた売り場は、見た目にも楽しく、つい手を伸ばしたくなる魅力があります。
形もサイズもバラバラが魅力?ディスプレイ型真空パック食品
アメリカのスーパーでスモークサーモン売り場をのぞくと、日本と似ているようで違うパッケージに出会います。同じ真空パックではあるのですが、日本ではきれいに形をそろえた薄切りが平たく並んでいることが多いのに対し、こちらでは分厚い塊でパックされていることが多いです。厚みのあるサーモンは見た目のインパクトも抜群です(画像3)。

(画像3)
魚の加工品は形やサイズに個体差が大きいため、「見て選ぶ」楽しみがあります。さらにアメリカでは、ソースや中の詰め物まで一緒に真空パックされている商品も多く、味を想像しやすいのも特徴です(画像4)。日本ではソースは別添のポーションや小袋に入れることが多いですが、こちらの真空パックだと完成形がイメージしやすく、「簡単においしく調理できそう」と思わせてくれます。

(画像4)
サーモンだけでなく、ステーキ肉などでも同様に、厚みと形をしっかり保ったまま真空パックにされて売られていることも多いのです(画像5)。
この画像の肉の場合は、パックにミシン目が入っており、冷蔵保管時に台紙ごと切り離して省スペース化できるようになっています。台紙は大理石風の柄で、高級感や清潔感を演出しているのも面白いポイントですね。

(画像5)
真空パックで旨みも凝縮?「EPIC」のストリップシリーズ
厚みがなく、中身が薄い真空パックももちろんあります。
次にご紹介するのは、アメリカの自然派ブランド「EPIC」の食品です。このブランドは添加物を控えた高品質な肉製品やスナックで知られ、アウトドアやフィットネス志向の人々に人気があります。英語で「ストリップ(strip)」というと、ステーキ肉の部位の一種でもありますが、細長い形にカットされた食べ物のことも指します。
画像左から鹿肉、和牛(「wagyu」は今や英語圏でも通じる言葉です!)、そしてスモークサーモンが並びます(画像6)。

(画像6)
どれも一食分のサイズで、厚みは薄めです。このパッケージスタイルならゴミも小さく、少なく済むので、おそらくアウトドアや携行用を意識した設計なのでしょう(画像7)。

(画像7)
パッケージデザインは、図鑑を思わせるリアルタッチのイラストが印象的です。素材へのこだわりや、自然とのつながりを感じさせる雰囲気があり、ハイキングやキャンプを楽しむ層にも好まれそうです。
売り場でも丸ごと!丸焼き用冷凍ターキー
私の住むイリノイでは、野生の七面鳥がその辺の草むらをスタスタと歩いているのを見かけるくらい、それほど珍しい鳥ではありません。もちろん野生を捕まえてそのまま食べたりはしませんが、身近な鳥として存在感がかなり大きい鳥です。
サンクスギビングデイが近づくシーズンになれば、スーパーの冷凍ケースの中にスイカほどのサイズの丸ごとターキーがずらりと並びます(画像8)。

(画像8)
この包装形態で売られるのが一番ポピュラーと言えるでしょう。厚手のシュリンクフィルムとネットでしっかり包まれています。
購入後はこのまま自宅で冷凍保存します。食べる前日に冷蔵庫で解凍するか、冷水解凍も可能ですが、それでもかなり時間がかかります。
調理の際には、シュリンクフィルムの縁にある穴に指をかけて引き裂いて開封します。鳥類の肉のパッケージとしては、かなりダイナミックな仕様です。
リシール可能でフレッシュなミニトマトパック
日本ではミニトマトなど小さめの野菜や果物は薄手のプラスチックのパックに入っていることが多く、省プラスチックの観点からもよく見かけますが、アメリカでは厚手のプラスチックケースが多いように思います。
今回ご紹介するのは、その中でも少し変わったミニトマトのパッケージです(画像9)。

(画像9)
トップのシールは再封可能で、少しずつ使いたいときに便利です。底側の黄色いトレーをフタ代わりにして、一気に大きく開けることも可能です。
トレーには籠のようなモールドが施されていて、ミニトマトの収穫風景を思わせるデザインです。見た目からしてフレッシュさを感じさせ、思わず手に取りたくなるパッケージです。
卵パックの工夫!卵を守るパッケージ
日本では卵といえば薄手のプラスチックパックが一般的です。日本に帰国した際に手に取ると、その軽さと薄さに少し心許なさを感じることもありますが、それでも卵はしっかりホールドされており、割れたものを見かけることはほとんどありません。
一方、アメリカではパルプモールド(紙製)のパッケージが多いです。ただ、厚手ながら日本のようなプラスチック製の卵パックもあり、特に二重蓋で卵を固定する内蓋が付いたタイプは、輸送や取り扱いの衝撃から卵を守る工夫が施されています(画像10)。

(画像10)
全米ではどうなのかわかりませんが、少なくともイリノイ州では卵が割れていることが多いため、購入前に割れていないか店内でチェックする人も少なくありません。パルプモールドだと中身が見えず、その都度開けて確認する必要がありますが、透明なプラスチックパックならその点はラクです。
ニーズは確かにあるのですが、このようにまだ少し大掛かりな設計を必要としているからか、主流とはなっていません。日本にいると長年当たり前に使ってきたため気付きにくいですが、アメリカの厳重な設計の卵パックを使ってみると、日本の卵パックの薄く軽いながらもしっかり守る高い技術力に、改めて驚かされます。
最後に
日本では、牛乳といえば紙パック、カット野菜はピロー型の袋、といったように、生鮮食品や日用品には常識的な結びつきがあります。しかし、場所が変わるとその当たり前も変わります。アメリカでは牛乳はガラスやプラスチックのボトル、カット野菜は頑丈なプラスチックケースに入っているのが一般的で、日本での「当たり前」が世界共通のものではないことに気付かされます。
こうした違いは、家庭での保管方法や廃棄処理の方法の違いも影響しているのでしょう。最初はアメリカのパッケージは厚手でしっかりしているものが多くて大げさだな、と思っていたのですが、最近では捨てるにはちょっともったいないと感じるようになり、数回は何かとリユースするようになりました。
パッケージが変わると、生活の何気ない行動も変わるようです。
▼編集部おすすめ記事
アメリカの新ブランド専門のグローサリーストアでみるパッケージとトレンド
毎日の買い物で実現するSDGs。エシカル消費の先駆的スーパー「Good Earth」